
ブレーキ全般
ブレーキのメンテナンスについて書きます。長いです(^_^;)
この辺はどこのホームページでも紹介されていますので
書く必要があるのかな?なんて思いますが・・・・。
整備書は必ずご用意して熟読しておいて下さい
お約束として、ブレーキ関係は重要保安部品ですので安易に考えないで
下さい。自信の無い方、自己責任の取れない方は触るべきではないと
思います。作業完了後、静止状態でのフルード漏れの確認は勿論
低速での試運転を十分に行って下さい。
●ブレーキの構成部品(能書き)
マスターシリンダー
油圧を発生させるものです。
小さな部品ですが定期交換部品が含まれています。
Fのノーマルサイズはφ11です。Rはφ1/2インチです。
前後とも同じサイズのキャリパーですが腕力対脚力の違いや、
Rをロックしにくいようにピストンサイズを変えているのかと思われます。
キャリパーに応じてこのサイズを変えます。
最近のバイクのFマスターシリンダーには別体タンクタイプの物が
多く使われています。ブレーキフルードの交換時はやりやすいですね(^^)
あとは見た目の好みでしょうか?
面積比(油圧レシオ)
一部分の計算に誤りがございました。
お詫びすると共に訂正させていただきます(2003年7月)
ブレーキを交換する上でピストンの面積比の計算は必須です。
キャリパー・ピストン面積÷マスターシリンダー・ピストン面積
ノーマルやTZRのキャリパーは対向ピストンタイプですが
全てのピストンの面積ではなく片側のピストンの面積です
SDRのマスターシリンダーはφ11、キャリパーはφ38が2個あります。
19X19X3.14
------------ =11.93 これがノーマルの油圧レシオになります。
5.5X5.5X3.14
マスターシリンダーピストンに1という力が加わった場合、キャリパーには約11.9倍の力が加わります。
また、キャリパーピストンを1という距離を移動させたい場合は
マスターシリンダーピストンを11.9移動させます。
キャリパーやローターの歪みは11.9倍にもなってマスターシリンダーに
返ってきますのでシビアですね(^_^;)
例えば、キャリパーは同じでマスターシリンダーをワンサイズ大きなφ1/2インチの
物と交換したとします。(ブレーキレバー比は同じとします)
この場合油圧レシオは8.95になりますので、ノーマルより3割程握力が多く必要になり(同じ握力では利かない)
一方キャリパーピストンの移動距離は多くなりますのでタッチは良くなります。
移動距離が多くなるというのはブレーキの調整代が少なくなるということですので
コントロールが難しくなります。平常時は問題なくコントロールできていても
パニック時は握りゴケなんてこともありうるので極端に面積比を変える場合は注意が必要です(^_^;)
TZR250Rなどに採用されている異径4ptの総面積は2959.45mm2です。
φ34とφ27の組み合わせです。
面積比は1479.725÷マスターシリンダーピストン面積 になります
マスターシリンダーサイズ別面積
| マスターシリンダー径 |
φ11
|
φ1/2(12.7)
|
φ14
|
φ5/8(15.87)
|
| 面積 (mm2) |
94.985
|
126.613
|
153.86
|
197.708
|
油圧レシオ一覧
|
φ11
|
φ1/2
|
φ14
|
φ5/8
|
|
| ノーマル |
11.93
|
8.95
|
7.37
|
5.73
|
| TZR250R(3XV) |
15.58
|
11.69
|
9.62
|
7.48
|
ノーマルの11.93を基準に考えると、キャリパーを3XVの物に交換した場合
マスターシリンダーはφ1/2が妥当と推測されます。
φ11の場合は多少初期の立ち上がりは悪く(タッチが悪化)なりますが
特に問題ないと思います。
仮にマスターシリンダーをφ14の物に交換した場合はタッチは良くなりますが
その分握力が必要になりますし、コントロール幅が狭くなる傾向にあります。
φ5/8なんか付けた場合は相当握力を鍛えないといけませんね(;^_^A
30代男性の平均握力ってどのぐらいなんでしょうか?50kg位かな?
握力計なんて一家に一台ないでしょうからご自分の握力を把握している方は多くないような気がします
簡易的には鉄棒に片手でぶら下がり3秒程度落下せずにいられれば
ご自身の体重≦握力 になると思います(パニック時に近いかも)
両手でも直ぐに落下する方は握力がかなり足りないか、体重がかなり重いかもしれませんので
健康管理に注意なさって下さい(;^_^A
普段はフルパワーを使うことは多くありませんが、パニック時はそれ以上の力でブレーキ操作を
行うことになります。
これらの計算はあくまでもキャリパーとマスターシリンダーでの比較です。
ブレーキレバーの設計にも大きく左右されますので実際はこの限りではありません。
ブレーキホース
ノーマルはゴムでできています。これは定期交換部品です。
よりクオリティーの高い物でステンメッシュ(中身は樹脂)のものや
ホンダのCRに採用されている何とか素材(忘れました)という物も
あるようです。
ゴムホースの場合、油圧が発生した時点で多少膨らみます。4輪と違い
バイクの場合は繊細な指先でブレーキ操作を行うため、この僅かな膨らみですら
感じてしまうわけです。この膨らみが効率という意味では無駄になりますので
よりダイレクト感を望むのでしたらステンメッシュタイプに交換するのも
いいかもしれません。
Fブレーキには有効ですがRには無理して入れる必要はないと思います。
ロードスポーツの場合はRブレーキは補助的にしか使わないと思いますし
急制動時は直ぐロックしてしまいますから少し鈍い方が良い気がします。
ブレーキキャリパー
SDRの物は前後共対向2ピストンタイプです
キャリパーには片押し、対向タイプがあり、使われているピストンの数も
様々です2輪では1〜6個でしょうか?
コスト的には対向タイプの方が高価ですし、ピストン数が増えるほど
重くなります。片押しは比較的軽く作れるのでオフロード車に多く使われて
います。ブレーキシステムで有名なブレンボではピストンにアルミ合金や
高力チタン合金が使われています。
ちなみに重さは
●Fキャリパーノーマル(パッド無し) 722g
パッド(残量8.5mm) 214 g
●FキャリパーTZR250(パッド無し) 839g
パッド(残量7.5mm) 186g
●ブレンボ(キャスティング4pt、パッド無し)660g
パッド重量:分からず(^_^;)多分上記のTZRの物と同等かと思います。

さすがアルミピストンですね圧倒的な軽さです(^_^;)
しかし、装着にはキャリパーサポートが必要となりますので
重量的なメリットは相殺されてしまいます。ブランド性はブッチギリですが(^^)
ブレーキディスク
SDRにはFφ267、Rφ210のローターが採用されています。
ローターは外径が大きくなるほど制動力は増しますが、重量も
増えます。バネ下重量でもあり、回転体でもありますので
大型化は極力避けるべきと思います。(見た目はカッコいいのですが・・・)
SDRのFローターはワンピース物ですが、軽量化や安定した制動力を維持するために
最近のバイクにはアウターをフローティングした2ピースで構成(市販車はかしめに
近いですが・・・)し、インナーディスクを比重の軽いアルミ合金で作られている
物がほとんどです。

φ300前後のスズキのγ用のローターは1.4kgでした、SDRのは1.5kgあります。
アウターの材質にはステンレスと鉄製がありますが、後者は錆びやすいのと
減りが早いです。タッチは良いとされているようです(詳しくは知りません)
Rブレーキサポート
SDRのものはリジットタイプです。中にはフローティングタイプの物があります。
どちらが良いとは言えませんが、リジットタイプは制動時にRサスを縮める働きがあり
Rの車高を下げ前のめりになるのを防いでくれます。
一方フローティングタイプは、サスの動きを全く妨げません。
Rが沈まない分Fタイヤにより車重を掛ける(前のめり)ことができます。
フローティング=高性能という訳でもないのです。
ブレーキパッド
これの選択が最も悩みますね(^_^;)
色々試してみるのが一番かと思います。
トップページの「アンケートづくし」皆さんの使用されている物が
書いてありますので参考になるかと思います。
●オーバーホール
長い能書きになってしまいましたがここからが本番です(^_^;)
定期交換部品と指定されている物は以下の通りです
(交換しないと直ぐに利かなくなるものでもありませんが、なるべく替えましょう)
1年毎:ブレーキフルード
2年毎:マスターシリンダーインナー
2年毎:ブレーキキャリパーインナー
4年毎:ブレーキホース(ノーマルです)
ブレーキフルード
タッチが変だな、ブレーキの引きしろが多くなった
なんて場合は先ずフルードを交換しましょう。
能書き書き始めるとキリがありませんので割愛させていただきますが
フルードは湿気を嫌います。水分を含むと性能が落ちます
大気圧を保つためにリザーバータンクには外気と通じる通路が
あり、そこから湿気が入り込みます。
単純交換でしたらキャリパーのブリーダーに排出用のホース(金魚用のエアホースや
シリコンホース)を繋ぎ、ハンドルを左にいっぱい切った状態でレバーを握り
古いフルードを出しながら新たなフルードを注ぎ、
チューブから汚いフルードが出なくなるまで行います。
最後にレバーをチョコチョコ動かしてリターンポートからエアが出なく
なるまでエアを抜きます。この時にフルードが飛び散りますので
目などに入らぬようにして下さい。
注意点
リザーバータンクが空になるとエアを噛んでしまいますのでその前に継ぎ足します。
フルードを注ぐ場合はゆっくり入れて下さい。勢いよく注ぐとエアが混ざり
本末転倒になります(^_^;)
フルードは塗装面を冒しますので万が一フルードが塗装面に付着したら
すみやかにふき取り、作業終了時にはマスターシリンダー、キャリパー
周辺に水を掛けておいて下さい。
1リットルとかの大きなやつですと使い切れませんのでなるべく少ない容量の
物を買ってきて下さい(500ccでも相当余ります)
純正で100ccとかいうのがあった気がします。
一度開封した物は徐々に劣化しますので早いうちに使いきって下さい。
グレードはDOT3以上になります。
ブレーキパッド
摩耗限度(1mm以下になったら替えましょう)が近くなったら交換です。
選定はお任せします(^^)
新品は一皮剥き(粗めのサンドペーパーを窓ガラスに当てパッドを動かします)
エッジは鳴き防止のために落としておくといいかもしれません。
パッド裏面にはパッドグリスを薄く塗布しておくと鳴きには有効です。
キャリパーを外したついでにピストンの状態を確認します。
パッドを外した状態でブレーキレバーを数回握りピストンを少し出します。
(沢山出すとピストンが外れてしまいますので欲出さないで下さい)
この時に左右のピストンが均一に出るのが望ましいのですが、ひどい物に
なると片側が固着してしまっているものもあります。
そういった状態でしたらキャリパーのオーバーホールとなります。
こうなる前に・・・
パッドは徐々にしか減りませんから、ピストンの突き出し位置はあまり変化しません。
パッドカスなどがピストンに付着してピストンの動きを妨げたりします。
ブレーキクリーナーや洗剤と水でピストンに付着したゴミを落とします。
ピストンには錆はありませんでしょうか?側面が錆びていると
ピストンを押し戻した時にシールを傷つけてしまいますので注意が必要です。
錆のひどい物は交換しましょう。
新品パッドを組むにはピストンを押し戻す必要があります。
専用工具もありますが、古いパッドを仮組してタイヤレバーや
ドライバー等でこじってもいいです。
この時にブリーダーを緩めておけば軽い力でピストンは戻ります
フルードが出てきますので前記のホースを繋いでおいて下さい。
キャリパー取り付けの際は固定ボルトを軽く締めておいてから
(キャリパーの自重で動かない程度)タイヤを浮かせた状態で
ホイールを進行方向に回し、ブレーキを掛けてロックさせる動作を
2、3回繰り返すとキャリパーが理想の位置にきますので
その状態で本締めして下さい。
ブレーキホース
うーん、特に書くことありませんが、メッシュホースにした場合
アルミのフィッティングの場合は締め付けトルクに注意して下さい。
ホースを交換した場合はエア抜きが大変です(^_^;)
先ずマスターシリンダーのエア抜きをします(ブリーダー付きのボルトでしたら楽ですね)
私はホースを外した状態でやることがおおいのですが、指の腹でホース取り付け穴を
押さえてレバーを握った時は力を緩めてレバーを戻すときはエアを吸わないように
力を入れて行います。
レバーに手応えがでたらホースを接続して前記の交換時の要領で行います。
完全にエア抜きが完了したら、各ボルト類を規定トルクで締め付け、レバーを
握ったままの状態でガスケットから液漏れがないか確認して下さい。
ガスケットは安いので毎回交換しましょう(^^)
裏技:上記の方法ですと結構時間が掛かります。
フルードを加圧して一気に抜く方法もあります(エアが微妙に抜けていない時なども
有効かと思います)
プラスチックの注射器を用意して下さい(ホームセンター、動物病院などで買えます)
容量は30ccもあれば十分です。これをキャリパーのブリーダーに接続します。
ホースが抜けやすいので針金やインシュロック等で締め上げておいて下さい。
注射器にフルードをゆっくり注入してエアが入っていないか確認後
ブリーダーを緩めてフルードを圧送します。
リザーバータンクが溢れないように注意して下さい。
これで大方のエアは抜けるはずです。後はレバーをチョコチョコ動かして抜いて下さい。
あっ、ハンドルは左に切っておいて下さい。
おまけ
エアが抜けなくてお悩みの方へ
細かなエアはなかなか抜けませんのでフルード注ぐ時が重要になります。
ハンドルは必ず左に切っておいて下さい。
ホース内の壁面やホース接続部分に引っかかる場合が多いのですが
ホースを揺すったり、軽く叩いたりしてエアを浮かせるといいかもしれません
あとは根気だけです(^_^;)
マスターシリンダー・インナーキット
Fブレーキの説明とします。
レバーを外すとピストンの頭が見えます。
ダストブーツは引っ張れば外れます。
小さなスナップリングでピストンが飛び出さないようになっていますので
スナップリングプライヤーでリングを外します。この時リターンスプリングに
よりスナップリングにはテンションが掛かっていますのでピストンを
押し戻した状態で工具を使うと楽です(やりにくいですが・・・・)
ピストンが外れたらブレーキクリーナーや水で全体を綺麗に洗浄します。
乾いたら新品のインナーにカップグリス又はブレーキフルードを塗布してから
組み付けます。
キャリパー・インナー及びピストン
パッド交換でも書きましたがピストン側面が錆びている場合はピストンキットを
注文して下さい(51L-W0057-00) これにはシールも付属しています。
油圧が生きている場合。
パッドを外した状態でレバーを握り、ピストンを外します。片側だけ出てきてしまう
場合は根性で押さえつけてなるべく平均的に出るようにするといいです。
万が一片側のみ取れてしまったらウエスで養生してプライヤー等でくわえて抜きます。
この場合ピストン側面に傷が付いたら潔く交換して下さい(傷つきの可能性大です)
スナップリングプライヤー(軸用)でしたらピストンに傷は付きませんが、工具が
曲がるかもしれません。
油圧が死んでいる場合
エアの力で抜きます。私はエアコンプレッサーは持っていませんので
自転車の空気入れで抜きました。ビーチボール用?のアタッチメントを
ホース取り付け穴に差し込みエアを入れれば抜けます。外れる瞬間にピストン同士が
激しくぶつかり合いますので間にウエスなどを入れておくといいかもしれません。
この後シールを外し、シール溝等に錆や異物が溜まっていないか点検して下さい。
もし問題があるようでしたら、真鍮ブラシで溝を掃除しておくといいです。
清掃が終わったら水かブレーキクリーナーで洗浄して下さい。
乾燥したら各シールにカップグリス又はブレーキフルードを塗布して組み付け
ピストンも同様に組み付けます。はみ出たフルード、グリスは綺麗にふき取って下さい。
キャリパーを割ってオーバーホールしてもいいのですが、接合面のOリングは部品供給が
ありません。また締め付けトルクの管理もあるので分解しないのですむならやらない方がいいです。


エア抜きは1度で済むようにオーバーホールを決意されたら全て同時にやってしまった
方がいいかもしれませんね(^^)
素朴な疑問
ブレーキホースをメッシュタイプに交換するといいの?
ブレーキのタッチは向上します。これはホースの僅かな膨らみが
ブレーキタッチに影響します。重量的には多分重くなると思いますが
メリットの方が大きいと思います。
ローターを大きくするとブレーキは良く利くの?
ローターが大きくなるということはパッドの当たり位置が変わります。
同じ力でパッドをローターに当てた場合ローターの半径が大きくなるほど
ホイールを止める力が大きくなるので利きは良くなります。
●------------○
●------------------○
白丸に同じ重さの物を載せた場合に黒丸に掛かる力は下の方が大きいのと
同じことになります。
単純にキャリパーをTZRのような4ptタイプに交換するとどうなるの?
パッドの摩擦係数が同じと仮定すると、ピストン面積比から
制動力は多少上がると思われます(タッチは多少悪くなります)
タッチ向上のためにφ1/2インチのマスターシリンダーに交換した場合は
面積比はノーマルと変わらなくなるので制動力は基本的に変わらなくなります。
ただし、4ptの設計がピストンをより外へという感じで設計されている場合は
上記のローターを大きくしたのと同じ様な効果も期待できますが、実際に
ピストン位置を計測した訳ではありませんので・・・(^_^;)下図のA寸法になります。
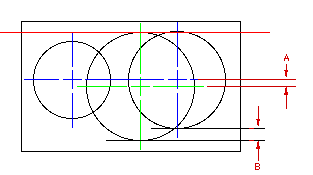
円の大きさはノーマルと3XVの物ですが、位置関係は適当です(;^_^A
またこれも推測ですが、4ptのキャリパーボディーは2ptから比べると
縦方向の寸法を小さく設計できるのでキャリパー剛性が上がり
開きにくくなるかもしれません。上図のB寸法分コンパクトに設計出来るかな?
まとめ
ロードレーサーなどは強力なブレーキを備えていますが、これはハイグリップなタイヤが
あるからこそ可能かと思います。
いくらブレーキシステムが凄くてもタイヤがブレイクした時点でブレーキの役目は終わりです(^_^;)
また、サーキットではほぼ同じタイミング、制動力で使用しますが
公道ではそういう訳にもいきません。いつ何が起こるか予測も付かない場合がほとんどです。
あまり過激なカスタムの場合はパニック時などは簡単にロックしてしまいますので
程々がよろしいかと思います。